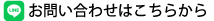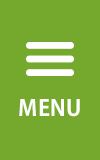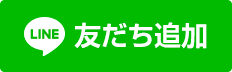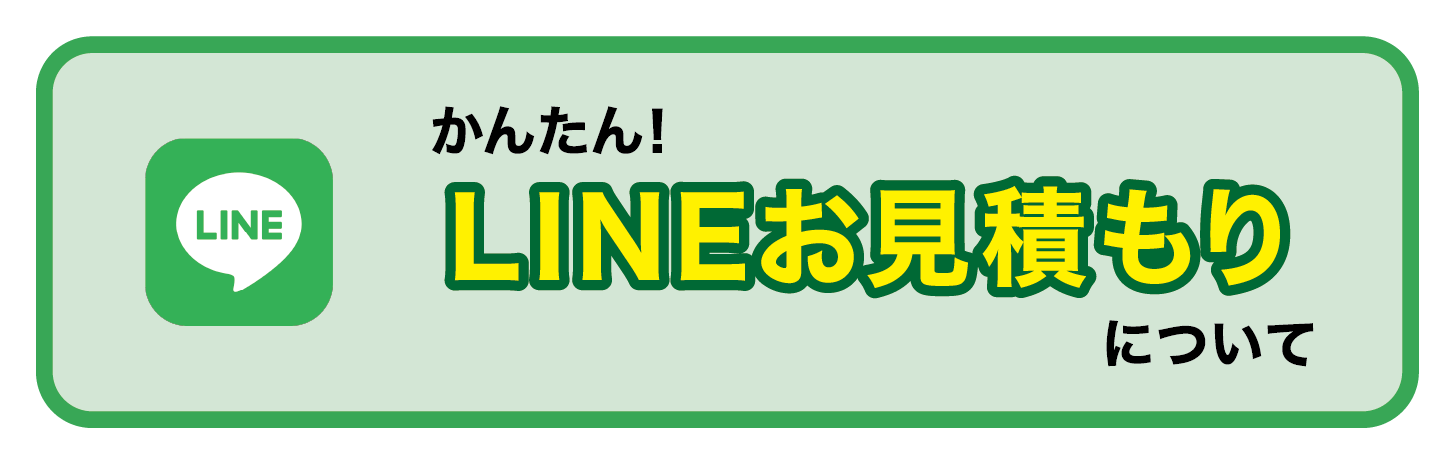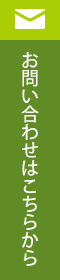生前整理をしたいなら!遺品・葬儀・相続について話し合っておこう
「終活」という言葉を耳にする機会が増え、ご自身の人生のエンディングについて漠然と考え始めた方も多いのではないでしょうか。
しかし、「具体的に何から手をつければよいのかわからない」と感じ、なかなか一歩を踏み出せないという声も少なくありません。
生前整理は、単なる身の回りの片付けではありません。
残されるご家族への負担を減らすという大切な役割はもちろんのこと、ご自身のこれまでの人生を振り返り、大切なものや必要なものを見極めることで、これからの時間をより豊かに、自分らしく生きるためのポジティブな活動です。
この記事では、遺品整理の現場で実際に多くのご遺族が直面してきた困りごとをランキング形式でご紹介し、今日からでも始められる具体的な対策をお伝えします。
私たちは札幌・苫小牧・旭川・函館を中心にして遺品整理をおこなう「遺品整理 想いて」です。現場にいる私たちだからこそ知る情報をまとめています。
この記事を読み終える頃には、生前整理への漠然とした不安が、具体的な行動計画へと変わっているでしょう。
Contents
死後に家族が困ることベスト5

遺品整理の専門家として数々のご家庭に伺う中で、ご遺族から「これを知っておきたかった」「これで本当に困った」という切実な声を耳にしてきました。ここでは、特に多かったお困りごとをランキング形式でご紹介します。
第1位:貴重品の置き場所がわからない
ご逝去後、ご家族は深い悲しみの中にありながらも、葬儀の手配や役所への届け出など、様々な手続きに追われます。
その際、真っ先に必要となるのが、預貯金通帳や印鑑、保険証券、年金手帳、不動産の権利書といった貴重品です。
「通帳はいつもタンスの一番上の引き出しにあったはずなのに…」「実印がどこにあるか、一度も聞いたことがなかった」
これらがどこにあるかわからないだけで、あらゆる手続きが滞ってしまいます。
銀行口座の凍結解除、保険金の請求、不動産の名義変更など、相続に不可欠な手続きを進めることができず、ご家族は途方に暮れてしまいます。
また、貸金庫の存在に気づかず、数年後に延滞料金の通知が届いて初めて知った、というケースもめずらしくありません。
今すぐできる対策は以下の通りです。
- 貴重品リストの作成と保管場所の地図作り:
まずは、ご自身が所有している貴重品をすべてリストアップしましょう。預貯金通帳(銀行名・支店名・口座番号も)、実印、印鑑登録カード、各種保険証券、年金手帳、不動産の権利書(登記済証)、株や投資信託などの有価証券、自動車の車検証、貴金属類、貸金庫の鍵など、思いつく限り書き出します。
そして、それらが「どこに」保管されているかを具体的に記します。「タンスの中」といった曖昧な書き方ではなく、「2階寝室、窓際の桐ダンス、向かって右側の上から3番目の引き出し、赤い布の袋の中」というように、誰が見てもわかるように詳細に記載することが重要です。簡単な見取り図を添えるのも非常に有効です。 - リストの保管場所を共有する:
作成したリストは、それ自体が非常に重要な個人情報です。厳重に保管する必要がありますが、ご家族が見つけられなければ意味がありません。信頼できるご家族(1人か2人)にだけ、「もしもの時は、この場所にあるファイルを見てほしい」と伝えておきましょう。エンディングノートに保管場所を明記し、エンディングノートそのものの存在を伝えておくのも良い方法です。
第2位:契約関連がわからない
電気、ガス、水道といったライフラインから、家賃や住宅ローン、固定・携帯電話、インターネット回線、新聞、クレジットカード、各種保険、そして近年急速に増えた動画や音楽のサブスクリプションサービスまで、私たちは数多くの契約を結んで生活しています。
これらの契約は、ご本人が亡くなったからといって自動的に解約されるわけではありません。ご家族が一つひとつ事業者へ連絡し、煩雑な解約手続きをおこなう必要があります。
「父がどんなサブスクサービスに加入していたか全くわからない」「クレジットカードが何枚あるのか把握できず、明細が届くたびに解約手続きに追われた」ということも。
そもそもどんな契約をしているのかわからなければ、解約のしようがありません。
放置すれば、利用していないサービスのために口座から引き落としが続き、ご家族の負担が増えるだけでなく、延滞が発生して信用情報に影響が及ぶ可能性すらあります。
今すぐできる対策は以下の通りです。
- 契約一覧表の作成:
現在契約しているサービスをすべて書き出しましょう。公共料金、通信費、クレジットカード(カード会社名、カード番号の下4桁)、各種ローン、保険、サブスクリプションサービス、習い事、ジムの会費、各種レンタルサービス、町内会費や組合費なども忘れないようにしましょう。
一覧表には、「サービス名」「事業者名」「連絡先電話番号」「お客様番号やID」などを記載しておくと、ご家族の手続きが格段にスムーズになります。 - 関係書類の一元管理:
契約書や毎月の請求書、領収書などを、クリアファイルやバインダーにまとめて一箇所で保管する習慣をつけましょう。「契約関係」とラベリングした箱を用意するのもよいでしょう。引き落としに使っている銀行口座やクレジットカードも一緒にメモしておくと、さらに親切です。
第3位:交友関係がわからない
ご家族は、故人が生前お世話になった方々へ訃報を伝え、感謝の気持ちを届けたいと願うものです。しかし、誰に、どこまで連絡すれば良いのか分からず、頭を悩ませるケースがあります。
「携帯電話の連絡先は何百件もあるが、誰が親しい友人なのかわからない」「年賀状の束を見ても、お付き合いの深さまでは判断できない」
ご本人にとっては、「この人には必ず伝えてほしい」「あの人には心配をかけたくないから、あえて知らせないでほしい」といった想いがあるかもしれません。
しかし、その意向が伝えられていなければ、ご家族は故人の大切な友人・知人に対して、失礼な対応をしてしまう可能性があります。
結果的に、ご本人の想いを叶えられないばかりか、人間関係のトラブルに発展してしまうことも考えられます。
今すぐできる対策は以下の通りです。
- エンディングノートに交友関係リストを作成する:
エンディングノートには、連絡先を記す専用のページが設けられていることが多くあります。そこに、訃報を伝えてほしい方の「氏名」「住所」「電話番号」「ご自身との関係性(例:大学時代の友人、会社の元同僚、趣味のサークルの仲間など)」を記載しておきましょう。
さらに、「思い出のエピソード」や「伝えてほしいメッセージ」などを一言添えておくと、ご家族が連絡する際に、故人の人柄や感謝の気持ちをより深く伝えることができます。訃報連絡が不要な方についても、その旨を記しておくとご家族の迷いを減らすことができます。
第4位:スマホやパソコンが開けられない(デジタル遺品)
今や、私たちの生活はデジタル情報と密接に結びついています。
スマートフォンやパソコンの中には、家族や友人との思い出の写真、メールやSNSでのやり取り、さらにはネット銀行の口座情報、ネット証券の取引履歴、オンラインサービスの契約情報、保有している仮想通貨など、有形無形の様々な資産が記録されています。
これらのデジタルデータは、持ち主が亡くなり、ロックを解除するパスワードがわからなくなってしまうと、永久に取り出せなくなってしまう可能性があります。これが「デジタル遺品」の問題です。
ご家族は、大切な思い出の写真を見返すことができないばかりか、ネット銀行に預金があることに気づけなかったり、有料サービスの解約ができずに料金が発生し続けたりと、金銭的な不利益を被ることもあります。SNSアカウントが乗っ取られ、悪用されるリスクも考えられます。
今すぐできる対策は以下の通りです。
- IDとパスワードの記録と管理:
最も重要な対策は、各種アカウントのIDとパスワードを記録しておくことです。ただし、すべてのパスワードを紙に書き出すのはセキュリティ上、不安が残ります。エンディングノートに「ヒント」だけを記しておく、信頼できる家族だけに口頭で伝える、パスワード管理アプリを利用しそのマスターパスワードだけを伝えておく、といった方法があります。ご自身のITリテラシーや家族関係に合わせて、最適な方法を選びましょう。 - デジタルデータの断捨離とSNSの終活:
元気なうちに、不要なデータやアカウントは削除しておきましょう。見られたくない写真やファイルは、ご自身の責任で処分しておくのが賢明です。また、FacebookなどのSNSには、死後にアカウントを追悼アカウントに移行したり、削除したりする設定があります。事前に設定しておくことで、ご家族の負担を減らし、アカウントの乗っ取りなどを防ぐことができます。
第5位:大切な遺品がわからない
遺品整理は、ご家族にとって精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となる作業です。特に、故人の持ち物一つひとつを手に取り、「これは残すべきか、処分すべきか」を判断する作業は、心の整理が追いつかず、なかなか進まないものです。
趣味で集めていた切手や古銭、長年書き溜めた日記や手紙、手作りの作品など、その価値はご本人にしかわからないものもあります。
「父が大切にしていたらしい骨董品の価値がわからず、二束三文で処分してしまったと後から知って後悔している」「母の遺品を整理していたら、私宛の古い手紙が出てきて、危うく他の書類と一緒に捨ててしまうところだった」こうした判断の難しさが、遺品整理をさらにつらく、困難なものにしています。
今すぐできる対策は以下の通りです。
- 「想い」を書き残すエンディングノート:
エンディングノートや手持ちのノートに、「大切なものリスト」を作成しましょう。品物の写真や、どこにあるかを記し、「なぜ大切なのか」「誰に譲りたいのか」「どのように扱ってほしいのか」といったご自身の「想い」を書き添えておくことが何よりも重要です。あなたの想いが伝わることで、ご家族は迷うことなく、故人の意思を尊重した整理を進めることができます。 - 相続や形見分けの意思表示:
生前整理は、財産相続を考える絶好の機会でもあります。ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券、貴金属、骨董品などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も含む)をすべてリストアップした「財産目録」を作成しておきましょう。これは、後の遺産分割協議をスムーズに進め、相続税の申告においても非常に役立ちます。
また、高価なものでなくても、特定の品を特定の誰かに譲りたいという「形見分け」の希望があれば、その品と渡したい相手の名前をリストにしておきましょう。さらに、愛用していた衣類や書籍などを寄付したい場合は、「遺品寄贈先リスト」を作成しておくことで、ご家族はあなたの社会貢献への想いを繋ぐことができます。
生前整理でお困りの際は、私たち「遺品整理 想いて」にご相談を

ここまで、ご自身でできる生見整理についてお伝えしてきましたが、「何から手をつけていいかわからない」「価値のあるものかどうかの判断がつかない」と感じる方も少なくないでしょう。
そんな時は、決して一人で抱え込まないでください。
私たち「遺品整理 想いて」は、札幌・苫小牧・旭川・函館エリアを中心に、お客様一人ひとりのお気持ちに寄り添いながら、遺品整理の専門家としてお手伝いをさせていただいております。
この遺品整理の専門家で培った力は、生前整理にも役立てています。
私たちのサービスは、単に物を片付けるだけではありません。お客様との対話を何よりも大切にし、どれが「大切な品」で、どれが「手放す品」なのかを一緒に確認しながら、丁寧に仕分けを進めていきます。
ご自身では価値が分からない骨董品や美術品、貴金属なども、専門の査定士がその価値を正しく見極め、買取のご提案をさせていただきます。
ご家族への負担を減らし、ご自身のこれからの人生をより心穏やかに、そして前向きに過ごすための生前整理。
まずは無料のお見積もり・ご相談から、お気軽にお問い合わせください。地域に密着した「遺品整理 想いて」が、あなたの新たな一歩を心を込めてサポートいたします。

かんたん♪LINEお見積もり実施中♪
▼友だち追加はこちらから▼
▼詳しくはこちらから▼